こんにちは。K2 College大崎です。
「ファンドを乗り換えました」と聞くと、証券口座で投資信託を一度売却し、別のファンドを買い直すことを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、海外積立型の投資商品では、その「乗り換え」が少し異なる仕組みで行われており、特に税制面で大きな差が生まれます。
今回は、海外積立商品の柔軟性と強みを解説していきます。
- 動画解説
- 「スイッチング」と「売却・購入」は何が違うのか?
- スイッチングの最大のメリットは「非課税での戦略変更」
- 海外積立商品の「柔軟性」を投資戦略に活かす
動画解説
「スイッチング」と「売却・購入」は何が違うのか?

「スイッチング」という言葉は、投資信託を入れ替える行為を指す際によく使われますが、実はすべてのケースに当てはまるわけではありません。特に混同されやすいのが、証券口座での売却・購入と、海外積立商品のスイッチングの違いです。
たとえば、SBI証券や楽天証券で投資信託Aを売却し、その資金で投資信託Bを購入した場合、それは「売却」と「購入」という別々の取引です。一度、保有資産が現金化されるため、基本的に売却益に課税されますし、次に何を買うかも投資家が自ら判断しなければなりません。
一方、海外積立型の投資商品では、ひとつの契約内で複数のファンドを保有・運用する仕組みになっており、ファンドを入れ替える行為は「契約内での資産の組み替え」として扱われます。
つまり、投資信託Aを売却して投資信託Bに変更しても、「同一契約内の運用方針変更」に過ぎず、課税対象とはなりません。
この「契約枠内で完結する設計」は、保険ベースで作られている海外積立型商品の特徴です。だからこそ、「売却・購入」ではなく「スイッチング」と呼ばれるのです。
この違いを理解しておくと、海外積立商品ならではの柔軟な運用設計が、どれほど魅力的かが見えてきます。
SBI証券などでファンドを入れ替えたら、それはスイッチングですか?
いいえ。
証券口座での入れ替えは「売却→購入」の2つの独立した取引であり、スイッチングとは呼びません。
スイッチングの最大のメリットは「非課税での戦略変更」
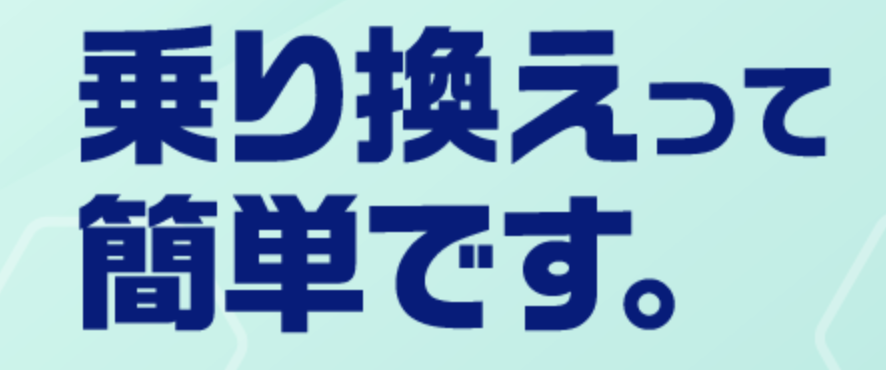
スイッチングの最も大きなメリットは、ファンドの乗り換え時に利益が出ていても課税されないという点です。
日本の証券口座では、ファンドを一度売却して別のファンドに乗り換える場合、売却益が出ていればその都度課税(通常20.315%)が発生します。これが、長期投資において“複利の力”を削ぐ原因になることは見過ごせません。
もっとも、現在の日本には「新NISA制度」が整備されており、一定の枠内であれば利益が非課税となるため、多くの個人投資家にとって強力な制度です。実際、NISAを活用することで、成長投資や分配金投資も非課税で運用できるのは大きなメリットといえます。
しかしながら、NISAには「非課税投資枠」という上限が存在します。たとえば成長投資枠は年間240万円まで、つみたて投資枠は年間120万円までという制限があり、長期で積み上げていけばいずれ枠を使い切ることもありえます。
一方で、海外積立型の投資商品では、保険契約内であれば年間の拠出額や運用額に関係なく、スイッチングに課税されません。これは、あくまで契約の内部でファンドを入れ替えているだけなので「利益確定」とみなされないからです。
この「非課税での戦略変更」が可能であるという特徴は、NISAとはまた別の次元で大きな意味を持ちます。
たとえば、世界経済の流れを見て、株式から債券、債券からREITといった戦略的な乗り換えをしたいとき、タイミングを逃さずかつ税金を気にせず実行できるのは、長期運用における大きな武器となるのです。
NISAと海外積立は、競合するものではなく、役割が異なる別の制度と考えると良いでしょう。
NISAは「枠を活かす短中期の運用」、海外積立型は「長期的に育てていく運用プラットフォーム」。そのどちらも知った上で、自分に合った使い分けができる投資家が、将来的に有利なポジションを築けるのです。
NISAも非課税ですよね?海外積立とどちらが有利なんですか?
NISAは非課税ですが年間上限があります。
一方、海外積立は契約内全体を柔軟に非課税で入れ替えできる点が優れています。両方をうまく併用するのが宜しいのではないでしょうか。
海外積立商品の「柔軟性」を投資戦略に活かす

スイッチングの非課税メリットに加えて、海外積立商品はファンド変更の自由度が高いことも大きな特徴です。世界中の株式、債券、REIT、コモディティなど、多様なファンドにアクセスでき、投資環境の変化に応じて機動的に運用方針を変更することができます。
たとえば、リーマンショックやコロナショックのような突発的な下落局面では、リスク資産を一時的に債券ファンドに逃がし、落ち着いたら再び株式に戻すという戦略が、非課税かつスムーズに実行できます。
また、インベスターズ トラストの『Evolution(エボリューション)』といった多くのプラットフォームでは、年間何回までという制限はあるものの、スイッチングに手数料がかからない設計になっていることが多く、長期投資家にとっては極めて実用的です。
「いまは新興国などの成長市場に資金を振りたい」「リセッションが近いからディフェンシブセクターに寄せたい」といった、市場環境を読み取った戦略的判断を“税金の足かせなし”に実行できる。これは、複利を活かし続ける上で非常に強力な仕組みです。
相場が荒れたときに柔軟に動かせるのはありがたいですね。NISAではそれが難しいのでしょうか?
NISAでも売却・買い直しは可能ですが、その分、非課税枠を消費してしまったり、非課税枠を使い切ったりしてしまう場合もあります。
海外積立のスイッチングは「枠を使い切らずに回転できる」のが強みです。
日本の証券口座にはない「契約枠内での非課税リバランス」という仕組みは、長期的な資産形成において、思った以上に大きな差を生みます。
まとめ
- 課税口座ではできない非課税スイッチング
- NISAにない「契約枠内」での柔軟な資産移動
- 相場変化に応じた戦略転換がスムーズ
こちらから『海外投資入門書(マニュアル)』を無料でダウンロードいただけます。
著者プロフィール

-
投資アドバイザー
愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。
その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。
自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。
最近の投稿
 コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方
コラム2025年9月17日米国の債務リセット戦略とゴールド・暗号資産市場の行方 コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像
コラム2025年9月12日100万ドル超え予測!4人の著名なビットコイン支持者が語る未来像 コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは?
コラム2025年9月4日次のビットコインの波に備える:歴史が示す“仕込みのタイミング”とは? 個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法
個人年金保険2025年8月29日400万円の学資保険を使った賢い運用で、教育費支払い後も約3億円まで資産を増やす方法
この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30909/trackback


























