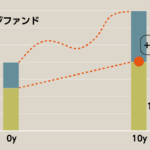男女の賃金格差(Gender Pay Gap)は、同一労働でありながら男性と女性の間で賃金に差が生じる現象であり、日本を含む多くの国が直面している重要な社会課題です。OECD諸国の中でも、日本の男女賃金格差は特に大きい部類に属しており、2022年のデータでは日本はOECD加盟国の中でワースト3位に位置付けられています。国際的に見ると、格差の縮小に向けた取り組みが進む一方、日本では依然として「見えない壁(ガラスの天井)」や「無意識のバイアス」が根強く存在しており、女性活躍推進政策が成果をあげ切れていない現状があります。
男女の賃金格差について詳しく教えてください。
以下で詳しく説明しますね。
- 賃金格差の現状と統計データ
- 賃金格差の要因:見えにくい構造的差別
- 国際比較:進む欧州、遅れる日本
- 政府と企業の取り組み:法制度と現場対応
- 今後の課題と展望:可視化から再設計へ
動画解説
賃金格差の現状と統計データ

日本における男女の賃金格差の実態を確認すると、以下のような統計が示されています。
• 厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(2023年)」によると、一般労働者の男女間賃金格差は約22.2%。
• 非正規労働者を含めた場合、格差はさらに拡大し、約25.0%前後に。
• OECD平均は約11.9%(2022年)であり、日本は2倍以上の格差を抱えている。
これは単に「女性の方が時給が安い」という単純な問題ではなく、役職への昇進率の違い、職種選択の傾向、勤務形態(正規/非正規)、育児・介護との両立困難など、複数の社会的・構造的要因が複雑に絡み合って生じています。
賃金格差の要因:見えにくい構造的差別

賃金格差を生み出す要因は多岐に渡りますが、主なものは以下の5点です。
(1) 昇進機会の格差
企業内で管理職や幹部職に就く女性の比率は依然として低く、部長級以上に女性が占める割合は約10%以下。昇進による賃金上昇の機会が少ないことが、結果的に格差を拡大させています。
(2) 非正規雇用の集中
女性はパート・アルバイトなどの非正規雇用に多く従事しており、労働市場での立場が不安定なため、年収ベースでは大きな差が生じます。
(3) 出産・育児によるキャリア中断
「出産退職」や「育休後の職場復帰時のキャリアダウン」が起きやすく、累積的なキャリア構築が困難になっています。これも長期的な賃金格差に寄与します。
(4) ジェンダーによる職種選択の傾向
女性は「事務職」「医療・介護」「教育」など、比較的賃金が低めの職種に集中する傾向があり、職種間賃金格差が賃金全体の男女差に影響しています。
(5) 無意識のバイアスと企業文化
「男性の方がリーダーに向いている」「女性は家庭を優先すべき」などの固定観念(アンコンシャス・バイアス)が根強く、女性の能力発揮の機会を狭めていることも見逃せません。
国際比較:進む欧州、遅れる日本

世界では賃金格差是正に向けた取り組みが進んでいます。
• アイスランド:2018年に「男女同一賃金義務法」が施行され、企業に同一賃金証明の義務付け。
• ドイツ:企業に対し、賃金に関する情報の開示を求める「賃金透明性法(2017年)」を導入。
• フランス・スペイン:男女比に応じた採用・昇進指標を企業に義務化。
• アメリカ:州レベルで「給与履歴の質問禁止」など、採用時点での格差再生産を防止
一方、日本では2022年から従業員301人以上の企業に男女賃金格差の開示義務が導入され、ようやく可視化が始まりました。しかし、開示の仕方が企業任せで不統一であり、格差是正のインセンティブにはなりにくいとの指摘もあります。
政府と企業の取り組み:法制度と現場対応

法制度の整備
• 女性活躍推進法(2016年施行)
• 育児・介護休業法の改正(2022年)
• 男女賃金格差の情報開示義務(2022年~)
これらの制度は一定の前進を見せているものの、企業文化や昇進評価制度の見直しが伴わなければ、実効性には限界があります。
企業の先進事例
• 資生堂:キャリア支援制度を強化し、管理職女性比率を20%以上に。
• カルビー:テレワークや柔軟な働き方の導入で、女性役員を複数登用。
• ダイキン工業:男性の育休取得率100%を目指すなど、家庭と仕事の両立支援に注力。
こうした企業努力が賃金格差の是正に貢献している事例も増えてきています。
今後の課題と展望:可視化から再設計へ

今後、賃金格差を解消するためには以下の5つの方向性が鍵を握ります。
1. 開示の義務化と標準化
企業に賃金格差の算定方法の標準化と定期開示を義務付けることで、透明性を高める必要があります。
2. 昇進評価制度の見直し
成果主義の導入だけでなく、多様な働き方に対応した評価基準への転換が求められます。
3. 男性の働き方改革と家庭参加の促進
育児休業を男女ともに取りやすくするなど、家庭内ジェンダー役割の見直しも不可欠です。
4. STEM分野など高付加価値職への女性参入支援
理系教育、起業支援、ITスキル研修などを通じて、産業構造と女性活躍のミスマッチを是正する必要があります。
5. 無意識バイアスの教育と啓発
企業・学校・行政において、ジェンダーバイアスを解消するための教育プログラムの普及が重要です。
基本給に影響度を与えるのは、高い順に年齢、勤続年数、性別のようですから、日本企業の年功序列的な昇給の仕組みが反映しているのが大きいですね。
女性は出産や育児でキャリアを中断することも多いですし、パート・アルバイトなどの非正規雇用を選択する方も多いですから、それも賃金格差に反映されます。
まとめ
- 男女の賃金格差は、単なる統計上の問題ではなく、構造的かつ文化的な課題が複合的に絡み合った現象
- 正規・非正規、職種、昇進、育児との両立、バイアスといった多層的な問題に対し、制度と意識の両面からのアプローチが求められている
- 日本では遅れていた格差是正の取り組みもようやく本格化し始めた段階にありますが、可視化から真の平等な評価制度への再設計へと進化させることが、今後の社会的課題と言える
- 賃金格差の是正は、女性だけでなく、企業、経済、そして社会全体の持続可能性を高める重要な要素とな
著者プロフィール

-
投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。
K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。
この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/30451/trackback